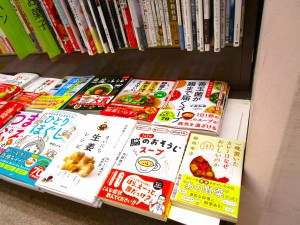さわや書店 おすすめ本
本当は、目的がなくても定期的に店内をぶらぶらし、
興味のある本もない本も均等に眺めながら歩く事を一番お勧めします。
お客様が本を通して、大切な一瞬に出会えますように。
-
no.5542023/6/24UP
本店・総務部Aおすすめ!
逆ソクラテス 伊坂幸太郎/集英社文庫
やはり上手い。思わず苦笑してしまうほど。短編集なので、本来あるべきストーリーや感情の説明など長い部分はバッサリ切ってある。それでもなお、いや、だからこそ明確に伝わってくるメッセージ。子供が主人公の物語5編。子供から大人までそれぞれに響く内容になっていると思う。やり過ぎないエンターテイメント性とメッセージ性の加減が見事だ。
個人的には「スロウではない」と「逆ワシントン」が良かった。「逆ソクラテス」で始まり「逆ワシントン」で終えるというのも小洒落ている。甘すぎない品のいいお菓子のように、すっと入って味わい深い。決して子供じみてはおらず、余韻はちょっとしたほろ苦さと共に。 -
no.5532023/6/21UP
本店・総務部Aおすすめ!
八月の銀の雪 伊与原新/新潮文庫
短編5編収録。個人的には「海へ還る日」と「十万年の西風」がなんか良かった。基本的には全て主人公の境遇と、それとは関係のない自然界の不思議が提示される。何が言いたいのか、それをどう受け取るかは読者次第。ストーリーと共に、読後はちょっと遠い目で地球のことを考えてしまう。
-
no.5522023/6/9UP
本店・総務部Aおすすめ!
ヒート2 マイケル・マン/メグ・ガーディナー/ ハーパーコリンズ・ジャパン
「ヒート」という本はない。『ヒート』とは著者のマイケル・マン監督による1995年公開の傑作映画だ。本書はマイケル・マン自身が初めて書いた映画の続編小説であり、完全に映画の空気感をそのままに、『ヒート』の前と後を描いた本格ハードボイルド・クライムノヴェルである。
この映画はもう何度観たことだろう。いつ観てもヒリヒリする映画の世界に引き込まれ時間を忘れて見入ってしまう。刑事のヴィンセント・ハナ、強盗団のニール、クリス、その妻シャーリーン。本書ではこの4人が主人公と言ってもいい。ただ、映画でのロバート・デ・ニーロの印象が強く残っているせいか、ニールの格好良さはやはり別格だ。映画を観る度にいつも最後“ニール逃げろよ”と願ってしまう一方、自ら破滅へと向かう一瞬の人間臭さにどうにもシビれる。本書もそんな、プロとしての仕事と人間としての魅力が随所に溢れた傑作だ。
『ヒート2』も映画化の話が進んでいるとの事。絶対に観ると決めている映画はそう多くはない。

-
no.5512023/6/2UP
本店・総務部Aおすすめ!
永遠と横道世之介 吉田修一/毎日新聞出版
終わってしまったな。と思う。三作楽しませてもらった横道世之介に感謝したい。この男、何の変哲もないフツーの男なのだが、なんだか妙に懐かしく、そして安心させられる。これまで、いろいろな登場人物が出てきては世之介を思い出し、当時の自分と今の自分を考えさせられている。この物語は主人公自身よりも、世之介を見て一瞬と永遠を感じ取る周りの人々のまなざしが美しいのだと思う。そして読者もその一員だ。
正直、最初の「横道世之介」だけでもうこの物語は完成されていると思う。「おかえり横道世之介」と完結編の本書は、いわばファンサービスのようなものだろう。間違いなくファンである自分にとってはもちろん何の異存もない。この三作は世之介以外の登場人物が全部別々なのでどれから読んでも問題はない。ただ、やはり最初の「横道世之介」は読んでほしいなと思う。それと、映画『横道世之介』。吉高由里子がいい。こちらも間違いなく傑作映画である。 -
no.5502023/5/24UP
本店・総務部Aおすすめ!
父を撃った12の銃弾 ハンナ・ティンティ/文春文庫
かなり凄惨な暴力描写の一方、静謐で詩的な様式美がどことなく漂う。あまり説明することなく、父娘の過去と現在のストーリーが行き来する中、表現されているのは生きるそのものの美しさか哀しさか。贖罪かあるいは逞しさか。風景や自然の描写が深く心に残る。
主人公の父娘よりも、死んだ妻で娘の母リリーが圧倒的な存在感を放つ。娘が生まれてすぐに亡くなってしまうのだが強烈な個性でその後も父娘に多大な影響を与え続けてゆく。この物語全体がリリーの物語と言ってもいいだろう。
真逆だからだろうか、ハードボイルドと青春・成長小説がうまく同居する物語はそうそうあるものじゃない。ひとつ挙げるとするならば、個人的には北野武監督の『キッズ・リターン』が思い浮かぶ。本書もそんなビターな傑作青春成長ハードボイルドのひとつだと思う。 -
no.5492023/5/15UP
本店・総務部Aおすすめ!
コメンテーター 奥田英朗/文藝春秋
ドリフのもしもシリーズのような“医者と患者”傑作短篇集。いやー、久しぶりの伊良部先生ですがお変りもなく、看護師のマユミちゃんと共にお元気そうで何よりです。なんとなくだらだらと通院するうちに、なぜか患者も読者も心が軽くなる。このトンデモ精神科医、完全に確信犯だと思う。すべてを分かった上で敢えての奇行だろう。ちょいちょい本質を突いてくる。サクサク読めるのでこの際、「イン・ザ・プール」から始めちゃってシリーズ全部を読んでしまう方がいいんじゃないかと思う。そこいらの胃薬や頭痛薬よりも、もしかすると効くかもしれない。
話は変わって、先日「午前十時の映画祭」にて『マルサの女』を鑑賞。以前から何度も観てはいるが、やはり名作である。前にも増して面白く感じた。特にラストの2人のやりとりはロケーションも含め見事で、いつ観てもシビれる。脱税する側と査察する側。双方ともにどこか病的なまでの執念と深い業を感じさせる。この2人も一度伊良部先生に診てもらったら、きっといいカウンセリングが受けられそうな気がする。しかし、人間どこか病気のぐらいが却って魅力的なのかもしれない。 -
no.5482023/5/9UP
本店・総務部Aおすすめ!
刀と傘 伊吹亜門/創元推理文庫
ミステリーとしての謎解きもさることながら、動機や心の動きへの洞察に時代小説としての奥深さを感じる。最終的には読者に委ねるような幕切れも、余韻を残しつつ再度物語に思いをめぐらされた。本書は時代小説とミステリー双方の良さが凝縮した、切れ味の良い見事なブレンドだった。
幕末から明治にかけての混乱期の物語だが、時代小説をあまり読まない人でも細かい事は気にせず読み進めて問題なく、またミステリーは関係ないという人にも安心して味わうことができる時代小説だと思う。時代小説だろうがミステリーだろうが、SFだろうが文学だろうがノンフィクションだろうがコミックだろうが、何であれ本という形式を通じて伝えたいところは、形は違えども一緒の部分が本質的にはあるのだと思う。 -
no.5472023/4/18UP
本店・総務部Aおすすめ!
町でいちばんの美女 チャールズ・ブコウスキー/新潮文庫
下品な短編がこれでもかと30話続き、さすがに食傷気味になる。閲覧要注意。でもなんだろう、この下衆なゴシップのようでいて振り切ったところの文学のような、やりすぎのコメディーのような。ハードボイルド調の語り口に、どうしようもない男達のどうしようもない会話。クズ野郎の中にもカス野郎の中にも最後に残る何かは、男の虚しさか哀しさか、もっと根源的な男の可笑しみか。表題作「町でいちばんの美女」がラストならば、終わり良ければすべて良しになったのかもしれないが、最初に来るからまた厄介だ。他が気になってしょうがない。ただ、これがラストだと最後までたどり着く自信はない。雰囲気としてはカルト的人気の映画『ビッグ・リボウスキ』や『インヒアレント・ヴァイス』に近いような気もする。
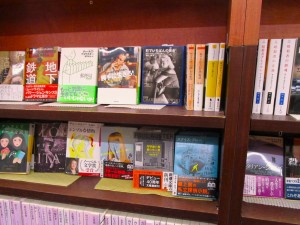
-
no.5462023/4/12UP
本店・総務部Aおすすめ!
モンテレッジォ
小さな村の旅する本屋の物語 内田洋子/文春文庫イタリア在住の著者。書店のルーツを探る旅はノンフィクションとして面白く、また美しい写真と共に紀行文として眺めるだけでも味わい深い一冊になっている。
どんな所にもその土地の風土や歴史があり、蓄積されてきた雰囲気は場所や人にどことなく表れる。読んでいて思うのは、現地の空気を吸ってみたいということ。本書を読む事は異国の文化に思いを馳せ、「本」というものの原点を想う旅になる。是非とも紙の質感や写真の趣、インクの匂いなども味わいながらゆっくりとページをめくってほしい。
テクノロジーは良くも悪くも進化を続け、後退する事は絶対にない。ただ、リアルの重要性もまた、今後増してくるだろうと思う。劇場やスポーツ競技場、コンサートホール、映画館、博物館、美術館。それらは単に映像を見たり音を聴いたりするためだけの空間ではない。あるいは自然に触れる事も、その道中も含め言葉では説明しきれないほどの価値がある。本屋とは何か。改めて考えさせられ、背筋の伸びる思いがする。
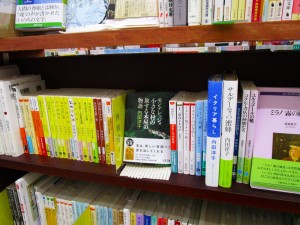
-
no.5452023/4/8UP
本店・総務部Aおすすめ!
一晩置いたカレーはなぜおいしいのか 稲垣栄洋/新潮文庫
たまに突然、なぜか無性にどうしても食べたくなる。辛さの主成分トウガラシは本来、鳥以外の動物に食べられないようにするための防御策として、辛さという毒を仕込んでいるのだそうだ。辛さは味覚ではなく痛み。ひーひー言いながら、人間は痛みを敢えて取り込んでいる。この痛みに対抗して排出させるために体は活性化し、脳内では疲労や痛みをやわらげるエンドルフィン(脳内モルヒネとも呼ばれる)まで分泌させる。どうりでたまに食べたくなる訳だ。マイナス面も意外なところで役に立つ、わからんもんですな。
カレー以外でも食べ物の意外な効用と植物の生存戦略が同時に学べて面白い。これから出てくる山菜も毎年必ず食べたくなる苦みなので、解明されていようがいまいが体にとって役に立っているのは間違いないだろう。辛さも苦さも子供には分かるまい。
巻末、印度カリー子の解説も流石。